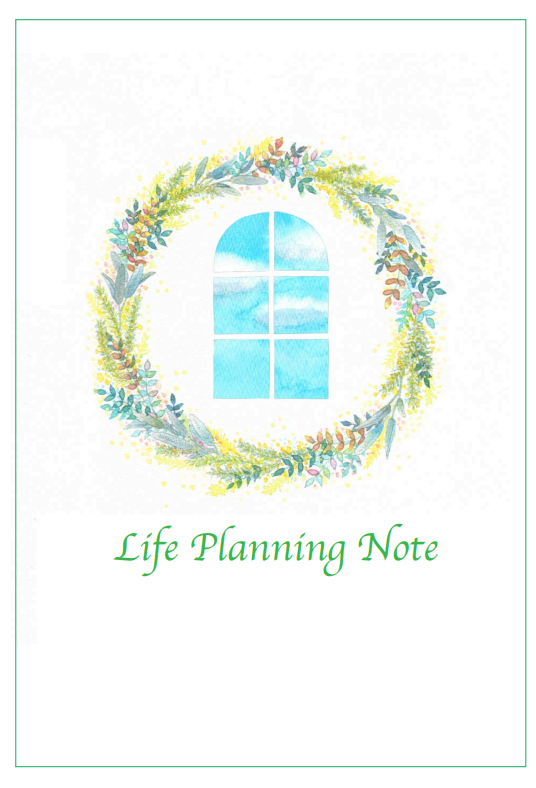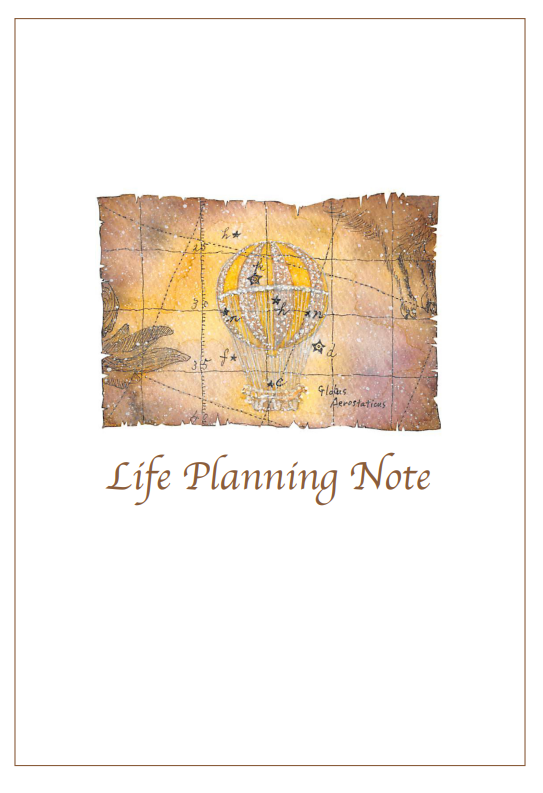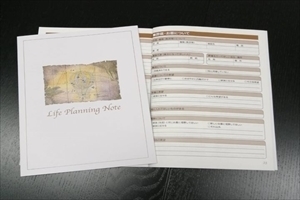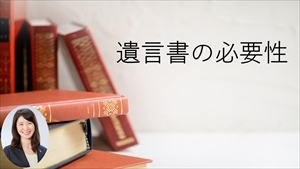自筆証書遺言の書き方は?
ポイントと注意点
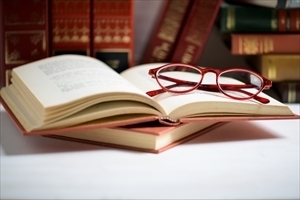
自筆証書遺言の書き方をご紹介するページです。
自筆証書遺言は正しく書かないと無効になる可能性があります。書き方のポイントと注意点についてご説明しております。
自筆証書遺言は自分で作成できる遺言です。
一人でも簡単に書けるのですが、書き方が法律で決められているため間違えると無効になってしまうこともあります。
せっかく書く自筆証書遺言が無効にならないよう、正しい書き方をご説明したいと思います。
無効にならない自筆証書遺言のポイントは次の4点です。
無効にならない自筆証書遺言のポイント
1.消せないペンで手書きをする
2.誰に何を相続するか明確に書く
3.作成年月日を書く
4.署名捺印をする
順番に詳しくご説明します。
1.消せないペンで手書きをする
自筆証書遺言は本文全文を手書きする必要があります。
パソコン書きは無効になりますのでご注意ください。
ただし財産目録はパソコン書きでも有効です。
特に不動産情報などは量が多いので手書きをするのは大変です。
パソコンで書いたものの他、登記簿謄本を別紙として添付することもできます。
楽ですし、書き間違いもなくておすすめです。
2. 誰に何を相続させるか明確に書く
相続させる財産、また相続させる人は確実に特定できるように書きましょう。
例えば預貯金であれば「○○銀行○○支店普通口座12345」などと書きます。
上述の別紙添付の方法であれば「別紙1の不動産」などと特定します。
相続させる個人の情報については、氏名だけでなく続柄や生年月日も書いておくのがおすすめです。
例えば子であれば「遺言者の長男横浜一郎(昭和45年1月1日生)」という具合です。
3.作成年月日を書く
作成年月日も明確に書いてください。
「令和6年9月12日」と日にちまで書きます。
日付が明確に書いていない遺言書は無効になります。
遺言書は何回でも書くことができ最新のものが有効とされます。
そのため作成日が入っていないといつ書かれたものか分からないので無効となってしますのです。
4.署名捺印をする
最後に署名をし、捺印して完成です。
遺言書は、現在でも捺印が必要となります。
印鑑は認印でも有効ですが、信憑性を上げるためには実印で捺印することをおすすめします。
以上が自筆証書遺言の書き方のご説明
でした。
最後に上記を踏まえた自筆証書遺言の
一例をご紹介します。
遺言書
遺言者横浜花子は、次のとおり遺言する。
1.遺言者は、遺言者の所有する 別紙1の不動産を遺言者の夫横浜太郎(昭和20年2月2日生)に相続させる。
2.遺言者は、遺言者の有する次の金融資産を遺言者の長男横浜一郎(昭和45年1月1日生)相続させる。
横横銀行本町支店 普通口座12345
東京銀行元町支店 普通口座23456
令和6年9月13日
横浜花子 ㊞
別紙1 ※1
登記情報 or
登記簿謄本のコピー
横浜花子 ㊞ ※2
※1 左肩あたりに「別紙1」「別紙2」…と番号をふり、本紙とのつながりを明確にします。
※2 別紙にも必ず署名と捺印をします。
自筆証書遺言は自分で手軽に作成でき、費用もかからないのが良いところです。
ただしその反面、次のようなデメリットもありますのでご注意ください。
●様式不備で無効になったり、紛失、改ざんの心配があります
● 家庭裁判所における検認手続きが必要となります。
●自筆証書遺言の保管制度を利用すれば紛失・改ざんの心配もなく、また検認は不要となりますが、交付請求が必要です。
より正確で確実な遺言を作成したい場合は、公正証書遺言をご検討ください。
遺言書の作成をご検討なら
遺言書の書き方セミナーのご案内
遺言書の書き方に特化したオンラインセミナーを開催します。
講座でお伝えするポイントを参考に、遺言書を正しくカンタンに作成いただけます。書き上げた遺言書は自筆証書遺言としてそのままお手元で保管するのはもちろん、法務局に預けることもできますし、公正証書遺言の原稿としても活用できます。
遺言書の必要性についてまずご説明し、基本的な書き方、遺留分や遺言執行者などの注意点、応用編、遺贈寄付の仕方など様々なテーマをご説明します。
会 場:オンライン
参加費:無料
特 典:講座をご受講くださった方にはオリジナルエンディングノートをプレゼント
~美しい挿絵に心が癒される、シンプルかつ充実したエンディングノートです~
遺言書のお役立ち情報
こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。