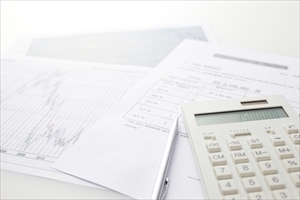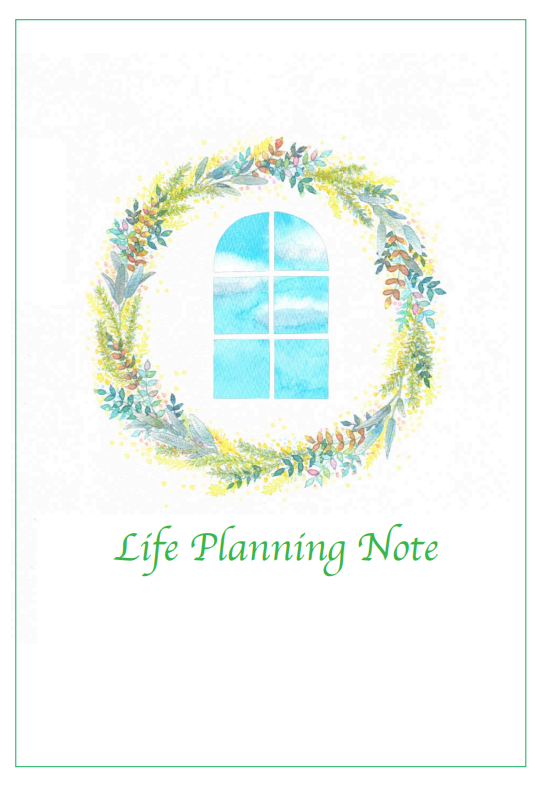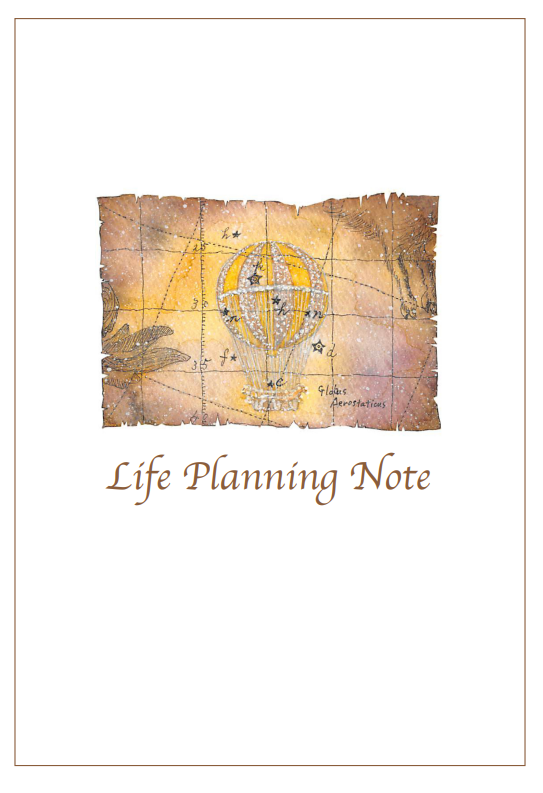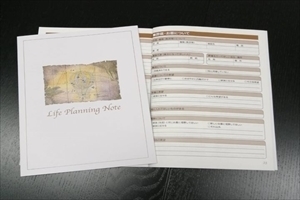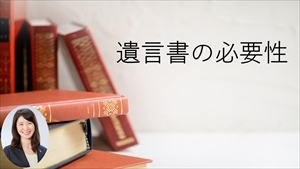遺産相続手続き代行のご依頼は
【横浜&オンライン全国対応】

突然やってきた相続でお困りではありませんか?
相続手続きは沢山の書類作成と、調べものの連続です。
役所に足を運び、銀行に問い合わせをして、大量の戸籍を取得し、協議書の書き方を調べて作成・・慣れないことばかりで、全部終わるまで1年近くかかることもあります。
煩雑で神経を使う手続きは全て専門家に任せてほっとなさいませんか?
相続の諸手続きは、書類作成の専門家である行政書士が全て代行いたします。リモートで対応でき、お費用はご遺産からの後払いですので相続人様の自己負担はありません。
相続手続き代行で相続のお悩みはおしまいにして、いつもの暮らしを取り戻しませんか?
グレイスサポートの遺産相続手続き代行は
1⃣ 丸投げで気楽
2⃣ リモート対応可能
3⃣ 正しい情報で安心
4⃣ 死後の事務にも対応
5⃣ 遺産から後払いで安心
の簡単相続手続きです。
こちらのページでは、相続手続きですることと、当事務所の遺産相続手続き代行サービスについてご紹介いたします。
大切なご家族をお見送りなさいましたこと、ご遺族の皆さまに慰めがありますようお祈り申し上げます。
ご遺族の皆さまは悲しみのさなか、下記のような手続に対応なさったことと存じます。
・死亡届の提出
・ご葬儀の手配
・埋葬の手配
・健康保険の手続
・年金手続き
・葬祭費の請求手続き
・世帯主の変更
・入院費の清算
・公共料金の引き落とし口座の変更
・クレジットカードの解約
・携帯電話の解約
・遺品の整理・・・
どうして相続手続きは難しいのか

そしてばたばたと月日が過ぎ、ほっと一息ついておられる頃ではないでしょうか。
しかし、ご遺族がなさる最大の手続はこれからとりかかる相続手続きなのです。
相続手続きとは、故人の財産を相続人が継承する手続きのことです。
これまでに対応なさってきた死後の手続は、ご家族のみで対応可能な手続きでした。
しかし相続手続きの場合は必ずしもそうではありません。
相続手続きは相続人全員の共同作業となります。
ここに家族の小規模化がすすんでいる今日の相続手続きの難しさがあります。
そのようなわけで、相続手続きは手付かずのまま放置という方も実際少なくありません。
事実しばらく前までは、相続手続きは放置しておくことも可能でした。
しかし平成26年に相続税の課税対象が広くなり、また令和6年からは相続登記も義務化されます。
金融機関の対応も厳格になっており、相続手続きを放置することは難しくなりました。
では、そもそも相続手続きとはどのようなことをするのでしょうか?
一般的な流れについてご説明いたします。
以下の手順は、相続人様が対応なさる場合も、代行させていただく場合も、基本的には同様です。
相続手続きの流れ
1.相続人の確定
相続に際し、亡くなった方のことを被相続人と言います。そして被相続人の財産を引き継ぐ人を相続人といいます。
相続人の順番は、法律で次のように決められております。
被相続人が結婚なさっていれば、配偶者は必ず相続人になります。
被相続人に、さらにお子さんとご両親とご兄弟がいらした場合は、子→親→兄弟姉妹の順番で相続人になります。
子、 親、兄弟姉妹が、同時に相続人になることはありません。
相続が発生したら、まずこの順番で誰が法定相続人にあたるかを確認し、裏付けとなる戸籍謄本を取得します。
被相続人の戸籍は出生からお亡くなりになるまでの一式が必要です。
被相続人がご高齢の場合は、昭和と平成に2回、戸籍の改製を経ておりますので、出生と1度の婚姻だけの経緯でも、最低4通の戸籍が必要となります。
それから相続人全員の現在の戸籍も取得します。
相続人が兄弟姉妹など傍系の場合は、被相続人とのつながりを証明するため、さらにその父母の戸籍もさかのぼって取得する必要があります。
戸籍謄本等の広域交付制度について
2024年3月より戸籍の広域交付制度が始まり、戸籍証明書・除籍証明書は直系相続人・配偶者であれば最寄りの役場窓口で一括請求できるようになりました。
詳細は各役場のホームページ等でご確認ください。
戸籍の広域交付制度が利用できる人
● 本人
● 配偶者
● 父母・祖父母など(直系尊属)
● 子・孫など(直系卑属)
※本人の兄弟姉妹は利用できません
※郵送や代理人による請求はできません
3.遺産分割協議

相続人と相続財産が確定したら、次はいよいよ、誰が何を相続するかを話し合いで決めます。
この話し合いのことを、「遺産分割協議」と言います。
遺産分割協議では、相続人全員が合意することで、任意の割合で遺産を分けることができます。
相続人の皆さまには様々なご事情があるでしょう。
皆さまが納得できる分け方が理想です。
遺産分割協議で遺産の分け方で合意ができたら、合意内容を遺産分割協議書にまとめます。
もし遺産分割協議で合意ができない場合は、家庭裁判所の調停・審判にて財産を分けることになります。
4.名義変更手続き
作成した遺産分割協議書を金融機関や法務局に提出し、内容に従い名義変更手続きをします。
それぞれの機関ではまた個別の手続書類があります。
窓口で書き方を教わりながら全て記入し、財産を継承する方の署名押印をして提出します。
遺産分割協議書を添付書類とともに法務局に提出し、継承者の名義に変更します。売却する場合でも、いったん名義変更してから売却することになります。
遺産分割協議書を添付書類とともに銀行の窓口に提出します。
遺産分割協議書の内容に従い継承者の名義に変更するか、口座を解約し継承者の指定の口座に振込を依頼します。
遺産分割協議書を添付書類とともに証券会社の窓口に提出します。
遺産分割協議書の内容に従い相続する有価証券を継承者の口座に移管します。継承者が口座をもっていない場合は新しく口座を開設することになります。
有価証券を売却する場合でも、いったん継承者が相続してから売却することになります。
したがって継承者が証券会社に口座を持っていない場合は口座を開設し、相続する有価証券を継承者の口座に移管してから売却することになります。
5.相続税の申告
相続税は、相続時にかかる税金ですが、基礎控除があり、相続財産が控除額を超過する場合のみ課税されます。
基礎控除の計算ですが、3000万+(600万×相続人の数)となります。
例)
相続人が配偶者と子ども2人の場合の基礎控除額は、
3000万+(600万×3)=4800万
相続財産が4800万円を超える場合のみ相続税が課税されます。
基礎控除を超える場合でも、様々な特例があり、必ず課税されるとは限りません。逆に課税されなくても申告は必要となる場合もあり、相続税の自己判断は難しいです。
相続財産が基礎控除を超えると思われる場合は、必ず専門家にご相談ください。
また申告の期限は被相続人がお亡くなりになった日の翌日から10か月以内ですのでご注意ください。
*細かいきまり事が沢山ある
上記でご紹介したのはごく基本的な情報で、相続には様々な細かい決まりがあります。
法改正もしばしばありますし、特例も多く、知らなかった!では済まされないこともあります。
一生の間に1回から数回、経験するだけの相続手続きでそれらを全て調べるのはとても大変です。
*期限がある場合も
預貯金の名義変更には今のところ特に期限はありません。
しかし、令和6年から相続登記が義務化されました。
また相続税の申告や準確定申告には期限があります。
時間がかって遅れると、税金が高くなってしまうこともあります。
*人間関係
相続はとてもデリケートです。
親子や兄弟でありながら、利害が対立する関係になるためです。
当事者同士で手続きをすすめる場合は、ちょっとした行き違いで関係が気まずくなり、トラブルに発展してしまうこともありますので注意が必要です。
遺産相続手続きの代行を依頼すると

このように煩雑で複雑な相続手続きを、専門家が全て代行いたします。
豊富な手続代行の実績がある専門家であれば安心で確実、スピーディーです。
こんなお悩みはありませんか?
*そろそろ何とかしないと
*事務手続きは苦手でやりたくない
*平日は仕事で休みがとれない
*相続人が多く、連絡をとるのが大変
*家族と相続の話をするのが気が重い
*一人だけ手続きするのは不公平
相続手続き代行サービスは手続きの専門家である行政書士が対応します。
相続人の皆さまのご負担を大幅に軽減し、スピーディーで円満な相続が可能です。
※相続人間で争いがないことが条件となります。
ー 代行できるお手続き ー
・相続人調査(戸籍収集)
・相続関係説明図作成
・財産目録作成
・遺産分割協議書作成
・銀行預貯金の解約及び払い戻し
・有価証券の相続手続き
・不動産登記の手配 ※司法書士と連携
・相続人への連絡
・相続人への遺産の分配
・相続税の申告の手配 ※税理士と連携
・不動産売却サポート
・遺品整理業者の手配
・二次相続対策のご提案
・その他の遺産相続にまつわる手続き
遺産相続の専門家にお任せください!
丸投げで気楽

相続が発生すると、お亡くなりになった方の戸籍の収集から財産の確定、費用の清算、各種名義書き換え、各相続人への分配、相続税の申告と、煩雑な作業が続きます。
グレイスサポートの相続手続き代行では、全ての手続きに専門家が対応。
ご相続人の皆さまにお願いするのは印鑑証明書の取得とご署名ご捺印のみです。
相続手続きは現役世代の方が担うことが多いと思われますが、お忙しい毎日のご負担にならないよう、スマート相続ではオンライン、郵送、お電話などのリモートで対応可能です。
※相続人間で争いがある場合はお引き受けできません。提携する弁護士をご紹介させていただきます。
正しい情報で安心
死後の事務にも対応

弊事務所の相続手続き代行では、遺産整理業務だけでなく全ての事務手続きに対応いたします。
万が一の際には、財産のことだけでなく、行政手続きや契約関係など、さまざまな事務手続きが発生します。
相続に限らず、あらゆる手続きをワンストップでおこないます。
お支払いはご遺産から

報酬、実費などのお支払いは全て、手続き完了後にご遺産から清算させていただきます。
相続人の皆さまのご負担はありません。
お費用の心配をなさらず安心してお任せいただけます。
※不動産の名義変更のみの場合はご負担があります。
| 自分で手続き | 相続手続き代行 | 金融機関 | |
|---|---|---|---|
| 手軽さ | × | ◎ | 〇 |
| 確実性 | △ | ◎ | ◎ |
| 対応範囲 | ◎ | ◎ | × |
| 費用 | ◎ | ○ | △ |
お費用のご案内
【基本報酬】 330.000円(税込)+ 実費
承継財産の額に応じ下記の計算額を頂戴しております(税込)
| 財産(積極財産)額 | ご相続人1人 | 2~3人 | 4人以上 |
|---|---|---|---|
| 5千万円以下の部分 | 1.1% | 1.32% | |
| 5千万円超1億円以下の部分 | 0.88% | 1.1% | |
| 1億円~2億円以下の部分 | 0.66% | 0.88% | お一人毎 |
| 2億円~3億円以下の部分 | 0.55% | 0.66% | ×1.1% |
| 3億円~5億円以下の部分 | 0.44% | 0.55% | |
| 5億円~ | 0.22% | 0.44% |
※遺産相続以外のお手続きについては別途お見積りさせていただきます。
※相続税申告報酬は含まれておりません。
※別途登録免許税、印紙代等租税公課等実費が発生します。
※お支払いはご遺産から控除するかたちでいただきます。事前のご負担は印鑑証明書の取得費用のみです。(ご遺産が不動産のみの場合はご負担があります)
※不動産売却をともなう場合は、別途お見積りさせていただきます。
※相続人間で争いがないことが条件となります。
このような方におすすめです
お仕事で忙しい方
相続手続きでは何度も役所や銀行に足を運ぶことになる場合が多いです。
平日にお仕事がある方ですと、手続きの度にお仕事をお休みしなければならないことも。
弊事務所の代行サービスなら、リモートで対応可能。ご質問やお困りごとのご相談も、メールやオンラインでご都合に合わせて対応させていただきます。
他の相続人と疎遠の方
親族であってもそれぞれに家庭があると疎遠になりがちで、お互いの経済状態などもよく知らなかったりします。
相続手続きはとてもデリケートな手続きですから、疎遠な親族と連携をとるのが気が重いという方は、代行サービスをご利用になると気持ちが楽でおすすめです。
距離がはなれている方
相続人の皆さまがそれぞれ遠方にお住まいの場合は、署名や捺印を揃えるのにその都度集まったり、書類を送りあったりで手続きが一層煩雑です。
代行サービスでは受任者が全て代行いたしますので手続きが円滑にすすみます。
銀行口座などが多い方
銀行手続きは各銀行毎に対応する必要があります。
つまり、各銀行毎に相続手続き書面を記入し、相続人全員が署名実印で捺印をし、遺産分割協議書や印鑑証明書、戸籍類などを添付して提出する必要があります。
しかも各行につき複数回足を運んだり、書類を送ったりする必要があります。
被相続人が預金口座をいくつもお持ちだった場合は作業が膨大となりますので、代行サービスのご利用をおすすめいたします。
事務手続きが苦手な方
相続手続きでは沢山の書類に目を通し、また作成することになります。
細かい文字を読むことや、事務手続きに苦手意識がある方、またご高齢で負担に感じる方は、代行サービスをご利用になるのがおすすめです。
代行サービスでは事務手続きの専門家が、迅速的確に対応いたします。
横浜市のNさん(40代男性)
O市のYさん(60代女性)
*不動産の売却まで、相続手続き一切をお引き受けしました
母が亡くなり、母が住んでいた実家を相続することになりました。
母は最期はホームに入っていたので実家は長いこと空き家でした。自分達は別に住まいがあるので、できれば売却したいと思いましたがどうしていいか見当もつきませんでした。知人からの紹介で、メールで問い合わせしました。
不動産の売却まで対応可能とのことでしたので一切お任せすることにし、委任状等を送ってもらって後は全部おまかせしました。相続税はかかりませんでしたが、不動産を売却したことによる譲渡所得税はかかりました。その申告も提携の税理士さんが担当してくださり、費用も全て売却費用から賄うことができてとても助かりました。
遺産相続手続き代行のご依頼は
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

1.お問い合せ
お電話、メール、お問い合わせフォームからお問い合わせください。
ご質問だけでも結構です。
お問い合わせには、迅速に回答いたします。
事務所もしくはご自宅などのご指定の場所でお話を伺うことはもちろん、リモートでの対応も可能です。
ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

2.必要書類をご用意
当事務所のサービスにご納得いただきましたら、委任状をお預かりし業務に着手いたします。
お客様のご状況、お考えを伺い、ご事情に応じた手続き書類をご用意します。
平行して必要となる証明書類の収集を行います。
全ての書類が整うまで数週間から1か月から数か月かかります。

3.ご署名
手続書類(遺産分割協議書、遺産整理の委任状)を作成しお渡しいたします。ご確認のうえご署名をいただき、印鑑証明書と共にご返送をお願いいたします。

4.ご遺産の分配
金融資産の解約、不動産の名義変更など、ご指示通りにご遺産を移す手続きを行います。
お費用を清算させていただき、相続人の皆さまにご遺産を送金して完了です。
相続税が課税される場合は、提携税理士が申告の手続きをいたします。
相続手続きセミナーのご案内
相続手続きは沢山の書類作成と、調べものの連続です。
役所に足を運び、戸籍の種類を調べて請求、定額小為替を購入し、宛名書きをし、協議書の書き方を調べて作成・・慣れないことばかりで、段取りよく手続きしないと全部終わるまで1年近くかかることも(;^_^A
この講座では、相続が発生したときに急いでしなくてはいけないことから、ひと段落してから行うべきこと、その手順について分かりやすくお伝えするセミナーです。
また相続手続きに欠かせない書面である遺産分割協議書の書き方について詳しくご説明いたします。
相続は一生の間に何度も経験することではないだけに、何から始めていいのか分からないという方がほとんどです。
いざ相続となったときに慌てないですむように、手軽なオンラインセミナーで備えておきませんか?
相続手続きの段取りが分かる!相続講座オンライン
会 場:オンライン(YouTubeライブ)※インターネット接続環境が必要です
参加費:無料
特 典:講座を受講してくださった方にはオリジナルエンディングノートをプレゼント
もしくは無料の個別相談
こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。