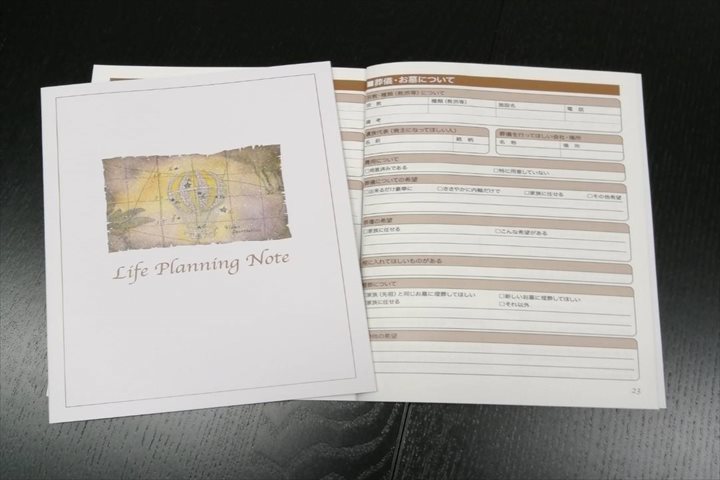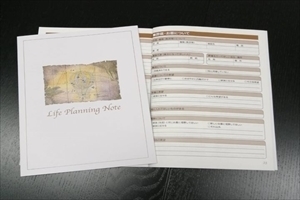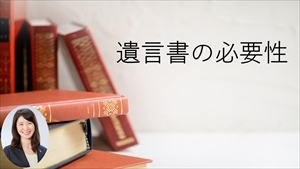海外在住日本人のための
遺言書作成法&国際手続き
国際結婚などで海外にお住まいの日本人の方でも、日本の方式で遺言書を書くことができます(遺言の方式の準拠法に関する法律第2条)。
国をまたぐ相続は場合は手続きが煩雑になりますので、円滑な相続のためには遺言を作成しておくことが大切です。
財産が日本と海外にある場合は、
・日本にある財産については日本式で
・海外にある財産については現地の方式で
それぞれ遺言書を作成しておくことがおすすめです。
日本国籍の方の相続には日本の法律が適用されますし、海外にある財産についても日本式の遺言で定めておくこともできますが、個々の物権の手続には所在地の法律が適用されます(通則法13条)。
したがって手続きの都合上、現地の方式で遺言されておくのが望ましいのです。
海外で作成できる日本の遺言書は?
日本方式の自筆証書遺言は証人の立会いも不要で、自分1人でどこにいても手軽に作成できます。
住所が海外であっても作成上なんら問題はありません。
遺言書の書き方も、要点さえおさえておけば特別難しいものではありません。
しかし以下にご説明するように検認の問題があります。
自筆証書遺言のデメリットである検認とは?
自筆証書遺言の場合は、遺言の執行に先立ち家庭裁判所にて検認が必要となります。
検認は、遺言書の改ざんなどトラブルを防ぐための法定の手続です。
検認の申し立ては、相続人や遺言執行者が管轄の家庭裁判所に行います。
海外在住の方の場合は、日本における最後の住所地の家庭裁判所に申し立てをすることになりますが、そこで確実に管轄が認められるか否か、定かでありません。
また検認には、遺言者(亡くなった方)の出生から死亡までの記載のある戸籍一式の他、相続人全員の戸籍の添付が必要ですが、相続人が外国籍の方で戸籍にあたる書面がない場合は、宣誓供述書など、戸籍の代わりとなる書面の添付が必要となります。
つまり検認は手続きのハードルが高く、円滑な遺言執行は困難といえます。
なお自筆証書遺言を法務局に預ければ検認は不要ですが、法務局に預けるためには日本に住民登録があることが条件です。
また法務局に預けてある遺言書情報の発行を求める際は(つまり、遺言書を法務局から受け取る際は)、検認と同じく戸籍類の提出が必要となります。
公正証書遺言がおすすめ
自筆証書遺言の場合は上記のような手続き上の問題があります。
確実な遺言の執行には公正証書で遺言を作成しておくのがよいでしょう。
外国在住の方の公正証書遺言は、在外公館で作成します。
作成方法は下記をご参照ください。
海外で公正証書遺言を作成する方法について、手続きの流れに沿ってご説明します。
1.遺言書の案文を用意する
遺言の内容を考えたら文章化しておきます。
日本の公証役場で遺言を作成するのであれば、公証人にメモ書き程度の概要を伝えれば公証人の方で遺言書の案文を作成してもらうことができますが、在外公館の領事は専門家ではないため起案などには対応しておりません。
そのため最終的に遺言にする内容で、文章をあらかじめ用意しておく必要があります。
2.身分証を用意する
領事館で公正証書を作成する際は、遺言者の身分証の提示が必要です。
日本国籍を証明するパスポートと、現住所を確認するための運転免許証などを用意します。
領事館に郵送する場合はコピーを取っておきます。
メールで送る場合はスキャンしておきます。
3.証人を手配する
公正証書の作成時には証人が2名、立ち会うことが法律で決められております。
証人は遺言の内容に無関係な人でないとなれません。
つまり、遺言者の家族や、受遺者(遺言で財産を受け取ることになる人)、領事館の職員などは証人にはなれませんのでご注意ください。
また日本国籍者である必要はありませんが、日本語を読み書きできることが必要です。
日本人のご友人に頼んだり、現地の日本人専門家などに依頼することになると思います。
証人になる方が決まったら、身分証の用意もお願いしておきましょう。
4.最寄りの領事館に連絡する
遺言書の案文、遺言者と証人2名の身分証が揃ったら、お電話やメールなどで、公正証書遺言を作成したい旨を領事館に伝え、作成日を調整します。
5.領事館で遺言書を作成する
予約した日時に遺言者、証人が領事館に行きます。
領事が遺言書を読み上げ、最後に遺言者、証人がそれぞれ署名をして完成です。
参考:遺言書の書き方
海外で公正証書遺言を作成する場合は上述のように、日本の公証役場で公証人が作成する場合とは異なり、遺言書の内容はご自身で確認する必要があります。
そのため在外公館に公正証書作成の予約をする際には、あらかじめ書き方・注意点などを調べて案文を用意しておくことが大切です。
こちらに遺言書の書き方の一例をご紹介いたします。
具体的な書き方、注意点は「遺言書の書き方」のページで詳しくご紹介しておりますので参考になさってください。
遺言書の見本
遺言書
遺言者 国際太郎は、次の通り遺言する。
1.遺言者は、遺言者の有する次の財産を、遺言者の妹横浜一子(昭和20年3月3日生)に遺贈する。※1
(1)土地
所在 横浜市遺言書区文例通一丁目
地番 ○○番○○
地目 宅地
地積 200平方メートル
(2)建物
所在 横浜市遺言書区文例通一丁目○○番地○○
家屋番号 ○○番○○
種類 居宅
構造 木造合金メッキ鋼板ふき平屋建て
床面積 50平方メートル
2.遺言者は、遺言者の有する次の財産を、遺言者の妻国際花子(昭和25年1月2日生)、遺言者の長男国際一郎(昭和53年2月3日生)に各2分の1の割合で相続させる。※1
(1)預貯金
遺言銀行 横浜支店 普通預金12345
文例銀行 東京支店 普通預金23456
3.遺言者は、この遺言の執行者として次の者を指定する。※2
横浜市遺言書区書き方1-23
行政書士法人遺言書事務所
2024年12月16日
現住所
国際太郎 ※3
被相続人(お亡くなりになった方)が海外在住であっても、日本における財産は、日本の相続手続きによって継承されます。
国をまたぐ国際相続の注意点についてご説明します。
公正証書遺言があると円滑
被相続人(お亡くなりになった方)が海外在住であっても、上記のように遺言書を作成なさっていれば、遺言の内容に従って財産が相続されます。
公正証書で遺言を作成しておき、遺言執行者に日本在住者を指定し遺言書正本を託しておけば、もしもの時は遺言執行者が手元の正本で速やかに遺言の執行に着手し、遺産を遺言で指定の相手に渡すことが可能です。
逆に遺言書がない場合は、相続人全員が話し合いで(遺産分割協議)で財産を分割し相続することになります。
遺産分割協議は相続人全員で行うため、海外在住の相続にも連絡をとり話し合って合意する必要がありますが、国内外に分かれる相続人が話し合いで合意にいたるのはとても大変です。
また以下のような書類を日本と海外でかわす必要もあり、手続きが大変困難となります。
円滑円満な国際相続のためには、ぜひ遺言書をご用意ください。
参考:国際相続の必要書類
日本における相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍に基づいて相続人を確定したうえで、相続人全員で作成した私文書である遺産分割協議書に基づいて、金融機関での相続手続きや不動産の名義変更をします。
相続人の中に海外在住の方がいる場合は、どのように対応するかご説明します。
相続人であることの証明
日本における相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍に基づいて相続人を確定します。
海外在住でも日本国籍をお持ちの場合は、戸籍によって相続人であることを証明することが可能です。
戸籍は本籍地のある市区町村の役場で取得します。
署名の真正の証明
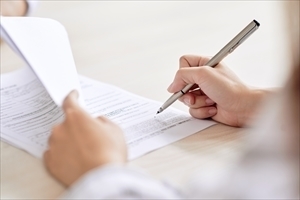
日本における相続手続きでは、遺産分割協議書に基づいて、金融機関での相続手続きや不動産の名義変更をします。
この遺産分割協議書には、相続人全員が署名をし、実印にて押印し、印鑑登録証明書を添付することで、金融機関や法務局は署名の真正の確認をします。
しかし印鑑登録及び印鑑登録証明書の発行は、一部の在外公館を除きほとんどの在外公館では取り扱いがありません。
そのため、日本国籍で海外在住の相続人の方は、印鑑証明書に代わる署名証明の取得が必要となります。
署名証明は、申請者の署名が領事の面前でなされたことを証明するものです。
署名証明の発給を受けるためには、
1.申請者が日本国籍を有していること
2.申請者本人が在外公館に出向いて申請すること
が必要です。
公正証書遺言作成サポートのご案内
幣事務所では、海外在住の日本人の方向けに、公正遺言の作成をサポートしております。
在外公館での遺言書作成は、案文の起案から証人の手配まで、お1人では対応がなかなか難しいものです。
幣事務所のサービスは在外公館での遺言書作成にワンストップで対応しており、ご自宅にいながら遺言書作成に必要な準備が全て揃います。
ご相談はオンラインでお伺いし、初回は無料です。
そろそろ日本の財産のことを考えておかないと・・・という方はどうぞお気兼ねなくお問合せください。
幣事務所の公正証書遺言作成サポートの3つの特徴についてご紹介いたします。
ワンストップ対応
幣事務所の公正証書遺言作成サポートでは、遺言書案文の起案から領事館との調整、証人の手配支援まで、公正証書遺言作成に必要な一切にワンストップで対応いたします。
ご相談者は調べ物をしたり、ご自分で文章を作成したりしないで済みますので、とても手軽で安心いただけます。
オンラインで完結

海外にお住まいでも、オンラインで日本からと変わらずにご相談いただけます。
全てオンラインで対応いたしますので、ご相談者の方には遺言書作成日に一度領事館に出向いていただくだけで済みます。
終活をトータルサポート
幣事務所は遺言書作成にとどまらず、シニア世代の皆さまのご不安に寄り添い、適切な制度や手続きをご案内するサポートを専門業務としております。
気がかりなことなどありましたら、お気兼ねなくお尋ねください。
報酬のご案内
| 海外公正証書作成支援 | 121,000円 |
|---|
| 遺言執行 | 385,000円~ |
|---|
※領事館に支払う公正証書作成料は含まれておりません。作成料は米国の場合40ドル程度です(日本の公証人手数料は数万から10数万円かかりますので大幅に安価です!在外公館で遺言書を作成する隠れたメリットといえます)。
※遺言執行の最低報酬は35万円(+遺言執行時の消費税)です。遺贈の場合は最低報酬は50万円です。
遺言者の死亡時におけるプラスの財産の額に以下の割合を乗じた金額とさせていただきます。
5千万円以下の部分 1.1%
5千万円以上1億円以下の部分 0.825%
1億円以上2億円以下の部分 0.55%
2億円以上3億円以下の部分 0.44%
3億円以上5億円以下の部分 0.33%
5億円以上の部分 0.22%
※本遺言執行に要する公租公課、不動産の相続登記に係る登録免許税、相続税申告に係る税理士の報酬、残高証明書の発行に伴う金融機関への支払手数料、その他遺言執行に伴う一切の費用は、報酬には含まれておりません。別途、遺産の中から控除して清算させていただきます。
※不動産の売却を要する場合は、売却価格の3.3%を報酬としていただきます。
※財産調査を要する場合や、内容の煩雑さにより加算させていただく場合がございます。
※消費税率は、遺言執行の時点の税率を適用させていただきます。
配偶者に全財産を遺す遺言書の作成をお手伝い

T国にお住まいのN様から、T国籍の配偶者の方に、日本にある全ての財産を遺す遺言書の作成をお手伝いしました。ありがたいメールをいただきましたので、ご紹介いたします。
「先生のお仕事は、“事が起きた時なるべく顧客に有利にように解決してあげる”というよりも”必ずだれにでも起きる事を想定して、残された者たちがトラブルにならないよう、煩雑な事務に困らないように事前に顧客を啓蒙する”とても有意義な仕事と思います。ですから何かの時に必要でしたら、私の事例を出してもらって結構です。先生のお役に立ちたいということもちろんでありますが、何より私どものような、海外に住んで周りに頼りになる専門家がいない、そんな老人達の助けになれば幸いという思いからです。私どもは素早く、やさしく対応していただける先生に出会えて幸せです。」
領事館での公正証書作成を遠隔でサポート

北米在住のA様ご夫妻から公正証書遺言作成サポートのご依頼をいただきました。
A様はお二人ともまだお若くていらっしゃいますが、もしものとき、お子さん方が身寄りのない海外に取り残されてしまうことがないよう、対策をご要望でした。
ご事情を詳細に伺い、もしもの時はお子さん方が日本に帰国し安心して暮らせるよう、負担付の遺言書作成をご提案しました。
案文を幣事務所で起案し現地の領事館に作成を依頼。作成日、証人の手配等を領事館、ご夫妻と協議、調整しました。
作成日当日、総領事、領事2名と、証人2名に立ち合いいただき、無事作成を終えることができました。
遺言書正本は幣事務所に航空便でお送りいただき、もしもの時に備えて金庫にて大切にお預かりしております。
-自分で遺言書を書くのが少し不安な方へー
遺言書の書き方セミナーのご案内です。
講座でお伝えするポイントを参考に、ご自身で遺言書を正しく作成いただけます。書き上げた遺言書は自筆証書遺言としてそのまま保管することも、法務局に預けることもできます。また公正証書遺言の原稿としても活用できます。
遺言書の必要性についてまずご説明し、基本的な書き方、遺留分や遺言執行者などの注意点、応用編、遺贈寄付の仕方など様々なテーマをご説明します。自分1人で遺言書を書くのは少し不安・・・という方は是非ご参加ください。
会 場:オンライン
参加費:無料
特 典:講座をご受講くださった方にはオリジナルエンディングノートをプレゼント
~美しい挿絵に心が癒される、シンプルかつ充実したエンディングノートです~
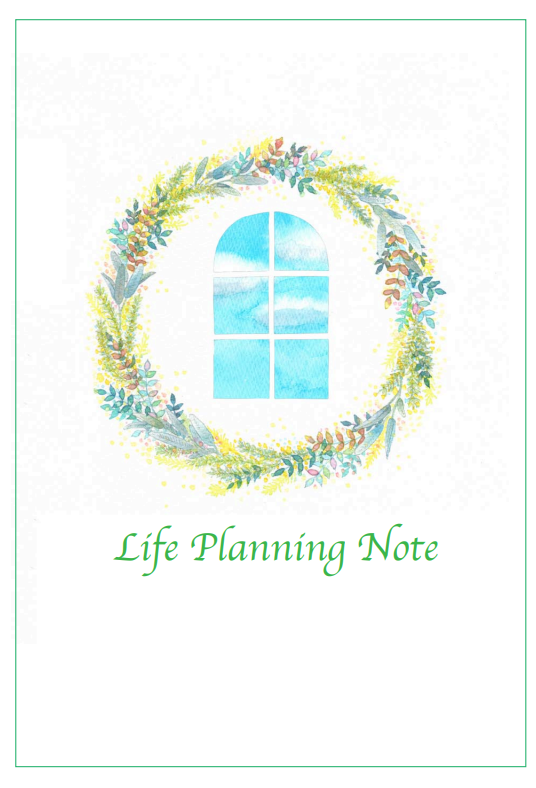
エンディングノート『ハーブ』
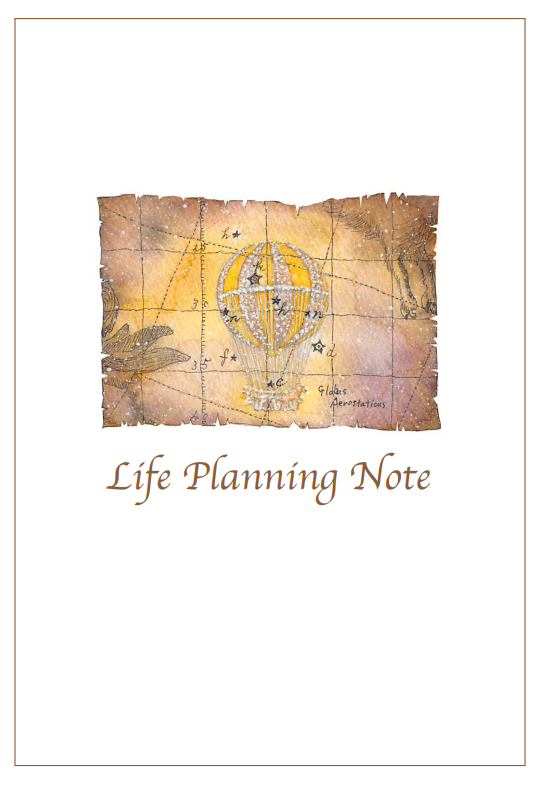
エンディングノート『星座』
こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。