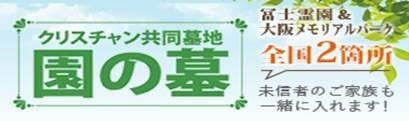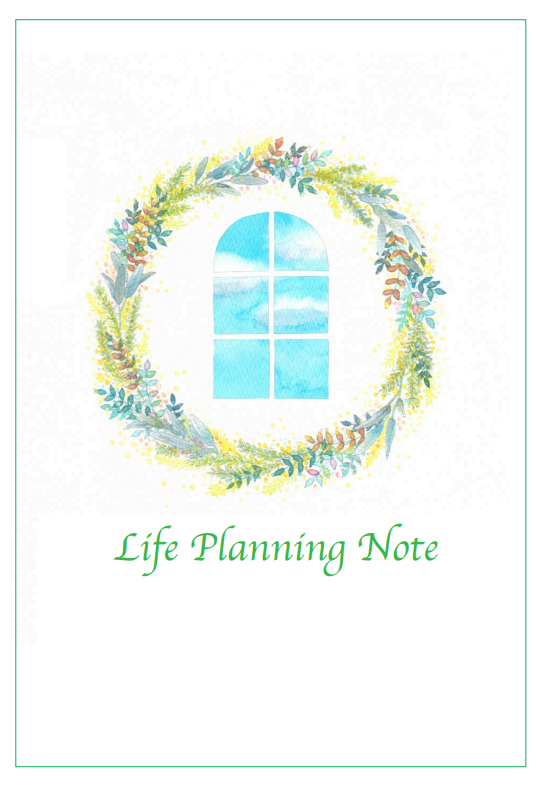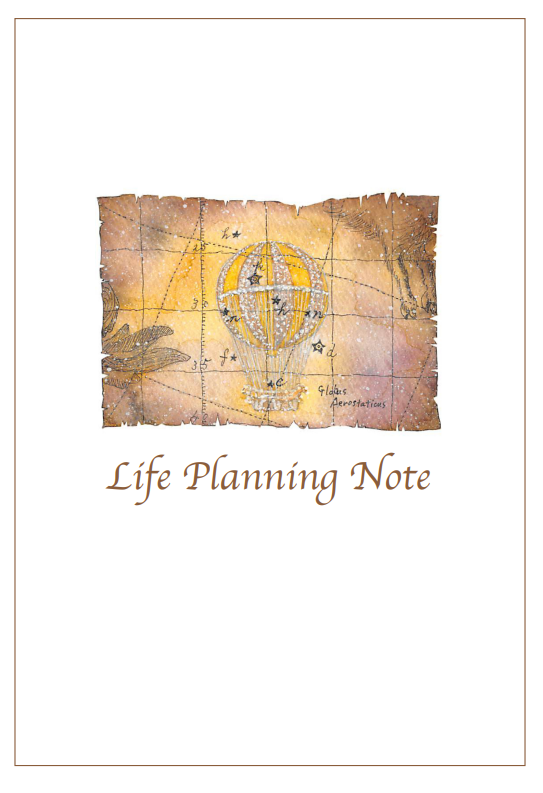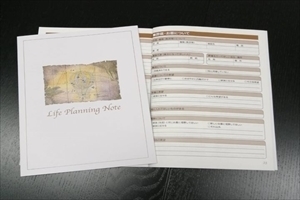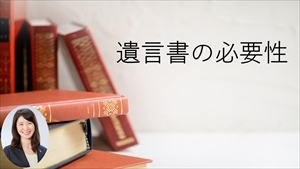墓じまいとは
費用と改葬&永代供養の手続き

墓じまいとは、今あるお墓を解体・撤去して更地にし、使用権をお墓の管理者に返すことです。
近年検討なさる方が大変増えておりますが、背景にはお墓を継ぐ人がいなかったり、お墓が遠方でお参りが大変だったり・・・という事情があるようです。このページでは、墓じまいの背景としまい方、改葬の行政手続き、また気になる費用についてご説明しております。
墓じまいとは
墓じまいとは、一般的には、今あるお墓を解体・撤去して更地にし、使用権をお墓の管理者に返すことをいいます。厚生労働省の統計によると、毎年約1万件のペースで増加傾向にありますが、増加の背景には何があるのでしょうか。
墓じまいの背景
*人口構成の変化
従来の日本のお墓は「山田家の墓」のように家名が刻まれ、家族親族の遺骨を埋蔵し子孫へ代々継承するのが通例でした。これはかつての家督制度に沿うかたちといえます。
しかし、少子化および家族の小規模化・単身化がすすむ近年は、従来のお墓の維持は担い手の不足で、困難となっております。
そこで将来のお墓の管理を懸念し、今のうちに墓じまいを選択していると考えられます。
*過疎化
また地方では、子世代が地元を離れ、親世代だけが残るという地域も多くあります。地元に住んでいる親世代が高齢となりお墓の維持が難しくなると、当面は子世代が帰省の度にお墓のお守りをするということになると思われますが、限界があります。
そこでやはり管理の継続を懸念し、墓じまいを選択することになると考えられます。
*選択肢の多様化
多様な個性が尊重される近年では、お墓に対しても自分らしさを求める傾向があるようです。このような変化をうけて、お墓にも従来のかたちにとらわれないさまざまな選択肢が登場するようになりました。
多様なお墓の登場で、子に負担をかけたくない、無理にお墓参りしなくてもよい、と考える方が増え、墓じまいの後押しをすることになったとも考えられます。
無縁墓にしないために
以上のような背景から、墓じまいはその必要性が高くなっているといえます。
お墓の承継者が途絶えたお墓を無縁墓といいますが、守る人がいないお墓は雑草が茂るなど次第に荒れていき、墓地の景観を害するだけでなく管理者の負担となります。
お墓の状態や連絡が付かないなど、お墓が無縁墓と判断されると、管理者により解体・撤去され、合祀墓で祀られることになるのが一般的なようです。
お墓の管理の困難が予想される場合には、無縁墓にならないよう、墓じまいを積極的に検討する必要があるでしょう。
*まずは丁寧に説明を*
墓じまいをする際に大切なのは、あらかじめ家族親族と話し合い、了解を得ることです。
お墓に対する価値観が多様化しているとはいえ、今でもお墓は代々受け継いでいくもの、という考えの方はおられます。
お墓を心のよりどころとしている方もいるでしょう。
家族や親族の了解を得ずに墓じまいをすすめてしまうと後にトラブルになりかねません。

どうして墓じまいをしたいのか、また墓じまいをした後どうするのか、を事前に丁寧に伝える必要があります。また事務的になりますが、後から苦情がでた場合に備えて決めた内容は書面に書きのこしておくと安心です。
家族親族の了解を得、墓じまいをすることが決まったら、次はお墓がある寺院や霊園に墓じまいの意向を伝えます。
付き合いの長い寺院などの場合は充分に配慮して伝えることが大切です。
*撤去事業者を探す*
お墓の解体・撤去をする業者も探す必要があります。石材店などの専門業者に依頼します。複数の事業者から見積もりを取り、費用とサービス内容を確かめてから頼むのが安心です。墓地によっては業者が指定の場合もありますので、事前に確認してください。
*墓じまいをする*
お墓から遺骨を取り出し、お墓を解体・撤去をします。
遺骨を取り出す際に、仏教では閉眼供養など、宗教儀礼を執り行うのが一般的です。
お墓の利用権を管理者に返還します。
お墓が仏教の寺院にあり檀家をやめる場合は、寺院にお世話になった挨拶・お礼(離壇料の支払い)をするのが通例です。
*改葬する場合は*
墓じまいののち、遺骨を別のお墓に移すことを改葬といいます。
改葬場合は、墓じまいと並行して改葬先を探します。また改葬には行政手続きが必要となります。
*散骨・手元で保管する場合は*
墓じまいののち、遺骨を散骨する場合、手元で保管する場合はそのための準備をします。
改葬手続きは必要ありません。
改葬する場合は、家族親族と話し合いのうえで今のお墓に事情を説明して了解をとり、新しいお墓を決めるのは勿論ですが、それだけで改葬はできません。
「墓地、埋葬等に関する法律」に則った改葬許可という行政手続きが必要です。
必要な書面をご紹介しつつ改葬許可の手順をご説明します。
改葬許可申請書
現在のお墓のある市区町村役所から【改葬許可申請書】を取り寄せ記入します。
ホームページからダウンロードできる役所も多いです。
埋蔵証明書
改葬許可申請書の所定の欄に、現在のお墓の管理者から証明をもらい【埋蔵証明書】とします。
あるいはお墓の方で発行する独自の埋蔵証明書の場合もあります。
改葬許可証
改葬許可申請書(+埋蔵証明書)を現在のお墓のある市区町村役所に提出し、【改葬許可証】を受け取ります。
↓
改葬許可証を現在のお墓に提示し、遺骨をお墓から取り出します。
※改葬許可証は新しいお墓に提出します。現在のお墓には提示するだけで、渡してしまわないようご注意ください
↓
改葬許可証を新しいお墓に提出し、遺骨を埋蔵します。
これでようやく改葬の手続が完了です 。
墓石の解体・撤去費用
お墓を解体し撤去するには業者に頼む必要があり、その費用がかかります。

費用は墓石の大きさや区域の面積、通路の幅、遺骨の数などにより変わります。
費用の平均は1㎡につき10万円程度のようです。
複数の業者から見積もりをとり検討するのが安心です。
お布施
仏教式ではお墓を閉じる際は、お坊さんに来ていただきお経をあげてもらうのが通例のようです(閉眼供養)。
この供養のお礼、お布施ですが、決まりのあるものではありません。その寺院との関係や、地域によってもさまざまですが、一般的には数万~10万円程度のようです。
離壇料
閉じるお墓が寺院にある場合は、墓じまいに伴い檀家を離れることになるわけですが、その際に離壇料を支払う場合があります。
離壇料もこれまでお世話になったお礼の気持ちとしてお支払いするものですので金額に決まりはなく、地域性もあります。
一般的には通常の法要の数倍、数万円から数10万円程度であることが多いようです。
もし金額に納得がいかなかったりトラブルになりそうな場合は、消費生活センターにご相談ください。188番で最寄りの消費生活センターにつながります。
次に、改葬する場合の費用のご案内です。
行政手続き費用
改葬する場合は、行政手続きに必要な書面の発行手数料が数100円から1,000円程度かかります。
このように墓じまいには少なくない費用がかかります。墓じまいの補助金を出している自治体もありますが、ごく一部のようです。
*親族間のトラブル*
墓じまいについて親族に相談や報告をする中で、お墓に対する価値観の違いから反対され、トラブルになることは少なくなりません。
親族が墓じまいに反対する主な理由としては、次のようなものが考えられます。
*石材店とのトラブル*
お墓の撤去は石材店が行います。費用の面で思わぬ高額であったり、逆に安価でも工事が粗悪では大変です。
石材店に依頼する前に、めんどうでも数社から見積もりをとり、信頼できるところに頼むのが安心です。
費用が安い石材店の場合は、レビューやコメントなどを参考にするのもいいでしょう。
*寺院とのトラブル*
寺院とのトラブルで多いのは離壇料についてです。
閉じるお墓が寺院にある場合は、墓じまいに伴い檀家を離れることになるわけですが、その際に離壇料を支払う場合があります。
離壇料もこれまでお世話になったお礼の気持ちとしてお支払いするものですので金額に決まりはなく、地域性もあります。
一般的には通常の法要の数倍、数万円から数10万円程度であることが多いようですが、高額な請求を受けてトラブルになる場合があります。
高額な離壇料を請求される背景には、説明不足による寺院側の不満の表れであることも考えられます。
現在のお墓では維持が難しい事情を丁寧に説明し、理解を求めましょう。
改葬する場合は、寺院から埋蔵証明書を発行してもらう必要もありますので、寺院との交渉は慎重に進める必要があります。
金額に納得がいかなかったりトラブルになりそうな場合は、最寄りの消費生活センターに相談するとよいでしょう。
墓じまいの後は、遺骨をご事情にあう方法で埋蔵することになります。
近年ではさまざまな埋蔵の選択肢がありますので、後の世代のことも考えて負担のない方法を選ぶことが大切です。
墓じまいの後、お参りしやすい場所に普通のお墓を新しく建てることも勿論あると思います。
相見積もりをとり、納得のお墓をご用意ください。
共同墓地(永代供養)
自然葬
自然葬とは、散骨などにより自然への回帰を願う葬送のことです。
自然との調和を大切にする近年の傾向から、墓じまい後のお墓として検討される方がとても増えております。
主な自然葬の方法としては、散骨と樹木葬があげられます。
墓標を設けず自然のなかに遺骨を撒くのが散骨で、木立の中に埋葬し、樹木を墓標に見立てるのが樹木葬です。
大きな違いは墓標があるかどうかという点です。
それぞれの特徴は、次のとおりです。
樹木葬(永代供養)
ここ数年、樹木葬を検討する方がとても増えております。緑豊かなやすらかな環境で、自然との調和を大切にする価値観とも合います。
多くは継承者が不要なのもメリットといえるでしょう。
一口に樹木葬といっても埋蔵の仕方はさまざまで、個別の区画に埋蔵する方法と、一つの大きな区画での中で個別に埋蔵する方法、区画がなく他の遺骨と一緒に埋蔵する方法があります。
一般的に個別の区画に埋蔵する場合は、樹木が墓標代わりの普通のお墓といえ、管理が必要なのも普通のお墓と同様です。
もっとも墓標が墓石ではなく自然の木立であるので、管理の手間や費用は墓石のお墓ほどかかりません。
区画がないものはいわゆる永代供養墓であることが多いようです。
海洋への散骨は遺骨を粉状に細かく砕き、海にまく方法です。生命の源である海に帰る海洋散骨も自然との調和を大切にする価値観に合いますし、後の管理が一切不要なため、特にお子さんがいないお一人様に検討される方が多いようです。

散骨は2022年現在、法律による規制が及んでおりません。しかし節度のある散骨を心がけることが大切です。
専門業者に依頼するか、船をチャーターするなどして、人気のない沖合で散骨するようにご配慮ください。
散骨というと撒くイメージがありますが、海上に撒くのではなく、水溶性の袋に入れて海中に沈めるのがマナーのようです。
また自治体によっては条例により散骨を規制している場合もありますので注意が必要です。
山林への散骨に対応している事業者もあります。個別の墓標は設けず山林の土壌に遺骨を埋蔵することで樹木の育成を促し、より積極的に自然への回帰を目指す埋蔵を行っている事業者もあるようです。
納骨堂(永代供養)
納骨堂は、遺骨を収蔵する建物です。永代供養のもの、継承するもの、いずれもあります。
収蔵の方法にもいろいろなタイプがあります。
ロッカー型のものは、遺骨を収蔵する個別のスペースが並んでおります。駅のロッカーと同じ形状ですが、扉が花柄だったり、家名が彫刻できたり、それぞれ工夫が凝らされております。
仏壇型のものは上部が仏壇になっていて、下部に遺骨を収蔵するスペースがあります。お値段は納骨堂の中でも高めになります。
自動搬送式の納骨堂は、立体駐車場のように、参拝スペースまで遺骨を納めた箱が自動的に運ばれてきます。
手元で保管する
遺骨を手元に置いておくのも一つの方法です。入れ物もいろいろな柄やサイズが揃っており、そのままお部屋に飾れるようなものもあります。
また加工サービスもさまざま登場しております。例えば人工ダイヤモンドに加工して、指輪などの装飾品にすることもできるようです。
※自治体によっては、遺骨を散骨や自宅で保管するためでも改葬許可を求められる場合があります。
永代供養とは、将来にわたる供養を遺骨を埋葬する霊園や寺院に一任することです。
お墓のあり方はさまざまで、共同墓地であったり、納骨堂、樹木葬であったり、特に決まりはありません。
永代といっても永遠の意味ではなく、多くの場合は33回忌までなどと期間が決められているようです。
供養の方法は霊園や寺院によりさまざまですが、定期的に合同で祭祀が執り行われることが多いようです。
永代供養には以下のようなメリットデメリットが考えられます。ご家族のご事情に応じ、墓じまいの後の選択肢の一つとして慎重にご検討ください。
*永代供養のメリット
永続的な管理:
永代供養墓を利用することで、お墓の管理や清掃などを行う必要がなくなります。業者によっては供花などのお供えも代行してくれる場合があります。業者に任せることで、自分自身や家族が亡くなった場合でも、お墓の管理について心配する必要がありません。
費用が格安:
永代供養墓では一定の使用料を支払うことで、管理が保証されるのが通例です。一度の支払いで済むため、一般墓よりも長期的に見ると費用が安く済みます。
安心感:
散骨や手元供養とは異なりお墓として存在しているので、家族の心のよりどころとして、お参りするお墓があるという安らぎがあります。
*永代供養のデメリット
施設による違い:
永代供養墓は、業者によってサービスの内容・質が異なります。比較的高価な永代供養墓でも、納得のいくサービスが得られないという場合もありますので、施設の選択には十分な検討が必要です。
継承者の理解:
永代供養墓は一定の使用料を支払うことで管理が保証されますが、永続的に供養がされるわけではなく最終的には合祀されます。継承者がいる場合は、そのことに対する理解を得るのが難しい場合があります。
墓じまいの後は、樹木葬や散骨などの自然葬を選択する方が多いようです。自然葬は後の管理が不要なため、お子さんがいないお一人様に好適です。
ところで埋葬後の維持管理が不要なのは良しとして、
お一人様の場合は、埋葬までの段取りも、生前に考えておく必要があります。
そこでご紹介したいのが死後事務委任契約です。
死後事務委任契約とは、死後に発生する諸々の事務手続きをあらかじめ委任しておく契約のことです。
死後事務委任契約を締結しておけば、委任者があらかじめ指定しておいた葬儀や埋葬を、受任者が滞りなく手配することができます。
また受任者は葬儀や埋葬の手配の他、行政への届け出や、未払金の清算などの事務手続きにも対応しますから、とても安心です。
死後事務委任契約では、以下のような事務を委任することができます。お一人様の方は、墓じまいをお考えの際は、死後事務委任契約もあわせて検討することが大切です。
死後事務委任契約でできること
*連絡対応
事前に指定された連絡先への訃報などの連絡
*ご葬儀対応
指定されたご葬儀、埋葬などの手配や見届け
*遺品整理
ご自宅の家財など、ご遺品の整理、形見分けなど。
*病院・施設の退去手続き
入院費用の清算、施設などの利用契約の解約、費用の清算など。
*契約の解約、費用の清算
電気ガス水道など生活インフラの契約、電話契約、クレジットカード、その他一切の生前の契約の解約手続き、費用の清算など。
*デジタル遺品の整理
サブスクやSNSなど、次々と増えるデジタル情報の整理。デジタル情報はネット上で管理されており、ご本人以外が把握することは難しいため、生前の対策が肝心です。
*丁寧に説明を*
墓じまいをする際に大切なのは、あらかじめ家族親族と話し合い、了解を得ることです。お墓に対する価値観が多様化しているとはいえ、今でもお墓は代々受け継いでいくもの、という考えの方はおられます。お墓を心のよりどころとしている方もいるでしょう。家族や親族の了解を得ずに墓じまいをすすめてしまうと後にトラブルになりかねません。
*見積もりをとる*
お墓の解体・撤去は石材店などの専門業者に依頼します。ご面倒でも複数の事業者から見積もりを取り、費用とサービス内容を確かめてから頼むのが安心です。墓地によっては業者が指定の場合もありますので、事前に確認してください。
*改葬する場合は*
墓じまいののち、遺骨を別のお墓に移すことを改葬といいます。改葬の場合は、墓じまいと並行して改葬先を探します。
また改葬する場合は、「墓地、埋葬等に関する法律」に則った改葬許可という行政手続きが必要となりますので、後で慌てないですむように、書類も並行して手配することが大切です。
*お一人様の場合は*
お一人様の墓じまいでは、墓じまいの後に自然葬や永代供養を選ばれる方が多いと思います。自然葬や永代供養であれば、後の管理負担がないためお一人様でも安心です。ただ埋葬事業者や霊園は、埋葬までの段取りには対応しておりません。別途死後事務委任契約を締結し、切れ目のない手配をしておくことが大切です。
コラム『終活30秒講座』
オンライン終活セミナー
ー終活手続き、何から始めるかお悩みの方へー
エンディングノートの使い方をご紹介しながら終活全般についてご説明するセミナーのご案内です。
お一人様向けまた資産の認知症対策としての任意後見制度、死後事務委任契約、争族対策としての遺言、お墓じまい、また相続手続きの基本についてお伝えします。
ご自身に必要な対策が見つかる終活セミナー、ご自宅から、どうぞお気軽にご視聴ください!
エンディングノートからはじめる!終活講座オンライン
会 場:オンライン
参加費:無料
特 典:講座を受講してくださった方にはオリジナルエンディングノートをプレゼント
~美しい挿絵に心が癒される、シンプルかつ充実したエンディングノートです~
こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。