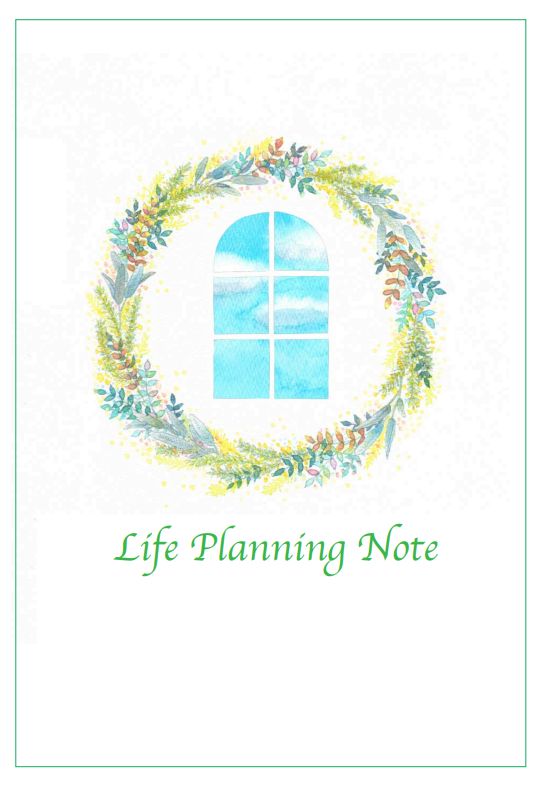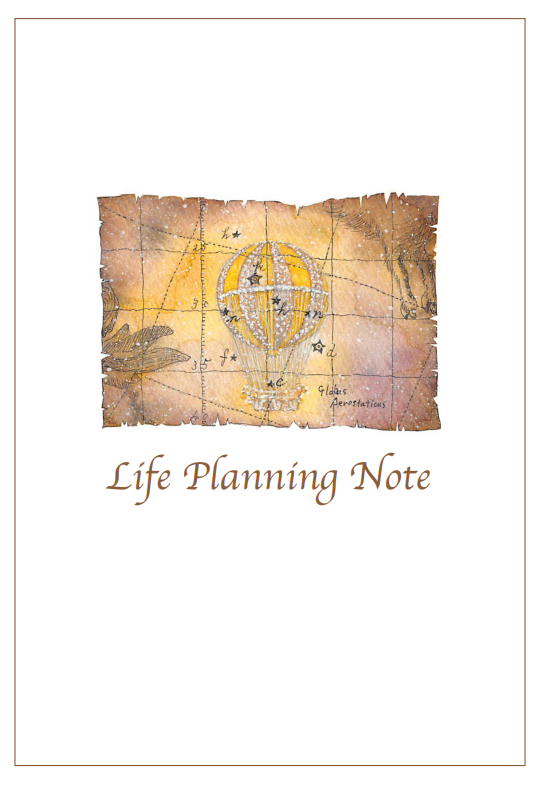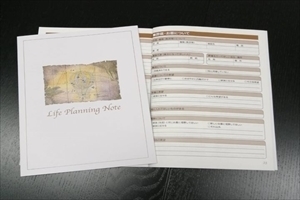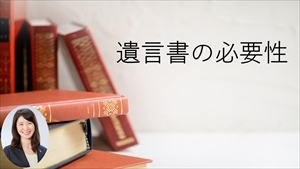遺贈寄付とは?
遺産を寄付する手続きについて
*遺言で行う寄付です
遺贈寄付とは、ご自分の財産の全部または一部を〝遺言により″法定相続人以外の個人や団体に無償で贈ることをいいます。遺言書は、書いたご本人がお亡くなった時に、書かれた内容に従って財産が継承される文書です。したがって、ご本人がお亡くなりになったときに遺言書で指定した財産が遺贈先に渡る寄付となります。
*無理なくできる寄付です
寄付には様々な方法がありますが、無理のない寄付ができるのが遺贈寄付の特徴です。
長寿社会はすばらしいですが、いくらお金があれば足りるのか、読めないところが気がかりです。
寄付したいけれど、あと何年生きるか分からないからどの位寄付できるか決められないと心配なさる方がいらっしゃいます。でもそのようなご心配は遺贈寄付では無用なのです。
その理由は、遺贈寄付は遺言書に書くことで行ますが、遺言書は、書いた後にもし財産が減ってしまっても、減った部分の効力がなくなるだけで 遺言書が丸ごと無効になることはないからです。
それにお亡くなりなった後も、ご葬儀その他でその方のための支出はあるものです。
それら全ての支出を控除し、もし残金があれば、それを寄付するのが遺贈寄付なのです。
さまざまな受遺団体
*遺贈寄付は、何をどこに寄付するかを遺言書に書く
前述のように、遺贈するには遺言書にその内容を明記する必要があります。一般的な遺書や覚え書、エンディングノートでは遺贈はできません。
遺言書とは、財産を遺す人が生前にご自分の意思で財産の配分などを指示する文書のことを言います。相続が発生し遺言書が無い場合、その遺産は法定相続人が相続することになります。しかしあらかじめ遺言書を用意しておくことで、ご自分の意思に沿った財産の分け方を実現することができるのです。
つまり遺言書は契約書などと同じく法的な効果を持つ文書です。この点で、死を覚悟した人がしばしば書置きする遺書や、エンディングノートとは全く異なります。
遺贈寄付はこの遺言書に、どの財産をどの団体に寄付するかを書くことで行う寄付の形です。つまり、遺言書が効力を発生するときに(つまり遺言者がお亡くなりになったときに)ご指定の財産がご指定の団体に贈られる寄付なのです。
*金額・時期は未定でよい
遺贈寄付には他の寄付にはない大きな特徴が二つあります。
一つは寄付の時期が未定ということです。
遺言書は、書いた方(遺言者)がお亡くなりになったときに指定した財産を指定した相手に移すための文書です。
ですから遺言で行う寄付である遺贈寄付も、遺言者が亡くなった時に行われることになります。
そのため寄付がいつになるかは当然のことながら決められないものなのです。
もう一つの特徴は金額も未定でよいということです。
遺言書を書いてから、書いた方がお亡くなりになるまで多くの場合長い時間があります。そしてその間、財産の変動は当然にあります。
したがって通常遺言書では通常、財産の額を指定して書くことはしません。
多くの場合、遺言書において金融資産は「全ての金融資産」ですとか「○○銀行○○支店の普通預金」などと指定します。
ですので遺言者がお亡くなりになったときその「全ての金融資産」や「○○銀行の普通預金」がどのくらいの額なのかはその時になってみないと分からないわけです。
遺贈寄付の場合も同じ理由で金額が決まっていなくてよいのです。
お一人様の遺贈寄付
*お一人様におすすめ
遺贈寄付はお一人様に特におすすめの終活メニューです。その理由ですが、相続人が全くいないお一人様が遺言書を遺さずにお亡くなりになると、その財産は国庫に納められることになってしまうからです。
相続人がいないため2022年度に国に帰属した遺産の額は768億9444万円だったそうです。
お亡くなりになった方が遺言書を遺していない場合、相続人がいれば遺産は相続人が相続します。
相続人にあたる人は法律で次のように決められております。
配偶者は常に相続人となります。
そして子→親→兄弟姉妹の順で配偶者と並び相続人となります。
また相続人の方が先に亡くなっている場合はその子、つまり孫や甥姪が相続人となります。
しかし相続人になれるのはここまでで、いとこなどは相続人になれません。
相続人がない遺産は、家庭裁判所が選んだ相続財産管理人が管理をします。
事実上の配偶者など特別な縁故者はここで財産の一部を受け取ることができる場合もあります。
そして最終的に全ての遺産は現金化され国庫に納められます。
このようにして国庫に納められる遺産は年々増加しており、9年間で倍以上になったそうです。
しかし、遺言書で指定すれば財産を相続人以外の個人や団体に継承することが可能となります。
ところで遺贈寄付は遺言で行いますが、身近な親族がいないお一人様の場合は遺言書の他、死後の諸々の事務一切を委任する死後事務委任を別途契約なさっておくと安心です。
*清算型の遺言書
お一人様の遺贈寄付におすすめなのは、清算型の遺言書を使って遺贈寄付をすることです。
お亡くなりなった後も、病院施設の清算や、ご葬儀その他でその方のための支出はあるものです。
それら全ての支出を控除した残金を遺すことを定める遺言書の書き方があり、これを清算型の遺言書と言います。
清算型の遺言書を書を使えば,、死後の支出も全て精算した残金を寄付することができますから、お身内に負担がかかることもなく、遺贈寄付にはお勧めの方法です。
遺贈寄付の注意点
公正証書遺言で
遺贈寄付は遺言で行う寄付であり、遺言は法律によって厳格に方式が決められております。
そのため不備があると無効になってしまう可能性があるので注意が必要です。
遺言書には主なものに公正証書遺言と自筆証書遺言があり、上記の例は自筆証書遺言のものになりますが、できれば公正証書がおすすめです。
公正証書は公証人が作成する公文書であり、様式不備の心配もありませんし、改ざんの防止、確実性という点でも優れているからです。
また遺贈をうける受遺団体の立場からも、相続人との万が一のトラブルを避けるために公正証書の方が望ましいと言えます。
公正諸書遺言は、自筆の遺言書や、どのような遺言にしたいのか記したメモなどをもとに公証人が作成します。
詳しい作成法はこちらでご紹介しておりますのでご参照ください。
遺贈先
遺言書には遺贈先を明記しますので、どの団体に寄付をするか決める必要があります。寄付先は一か所に限らず、何か所かに分けることも可能です。
遺贈する財産の内容によっては受け入れられない場合もありますので、事前に受遺団体に確認した方が望ましいです。
遺贈を受け入れている団体は様々あります。
国際的な慈善団体や公益法人、宗教法人、学校法人、社会福祉法人、認定NPO法人、それに自治体にも遺贈を受け入れているところがあります。
支援したい団体が遺贈を受け付けているか明らかでない場合は、当事務所で確認いたしますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。
医療活動団体を支援する、出身校に寄付をする、信仰している宗教団体、お世話になったシニア施設、ふるさとの市町村などに遺産を贈る・・・ご自身のお気持ちと相談しながらご検討ください。
包括遺贈と特定遺贈
遺贈する財産も特定する必要があります。金額は未定でも大丈夫です。また金額の大小は全くご心配いりません。少額でもありがたいものです。現金以外の不動産などを受け入れているかどうかは受遺団体によります。
遺贈の方法として、財産の割合を示して遺贈する包括遺贈と、特定の財産を遺贈する特定遺贈があります。
遺贈寄付する財産に不動産がある場合は、円滑な手続の観点から包括遺贈が都合良いと思われます。
遺言執行者
遺言執行者とは、遺言書の内容を実行する手続きを行う担当者のことです。遺言執行者は短単独で名義変更等の手続を行うことができます。
遺贈の場合は、逆に遺言執行者が指定されていないと、名義変更の手続きに相続人の関与が必要となります。
もしかしたら相続人の中には遺贈寄付について快く思っていない人もいるかもしれません。
したがって、相続人間の揉め事を回避し、円滑に手続きを進めるためには単独で手続きできる遺言執行者を指定しておくことが大切なのです。
遺言執行者には誰でも指定できますが(未成年と破産者は除く)受遺団体を遺言執行者に指定することは避けた方が無難です。利害関係のない第三者を指定するのがいいでしょう。
遺留分にご注意
法人に相続税はかからない
法人格のある団体に遺贈する場合は相続税はかかりません。相続税は個人に課される税金だからです。
不動産や有価証券を遺贈する場合は、譲渡所得税が課税される場合があります。前述の通り、このような場合に譲渡所得税を負担するのは受遺団体ではなく相続人となりますのでご注意ください(受遺団体が包括受遺者の場合は受遺団体が相続人の立場になります)。
不動産の特定遺贈の場合、受遺団体には不動産取得税がかかります。包括遺贈の場合は、不動産取得税はかかりません。
個人の場合は相続税がかかる
相続税は個人にかかる税金です。そのため法人格のない団体や個人に遺贈する場合は、相続税が課税される可能性があります。
譲渡所得税、不動産取得税は課税されません。
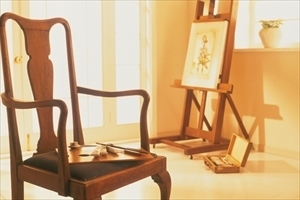
*遺贈先の相談ができる
自身の財産を、支援する団体や困っている方のために使ってほしい 。その尊いご意思の背景には、さまざまな思いが込められております。弊事務所は特定の受遺団体ではありませんので、公平な立場で傾聴の姿勢を大切に、丁寧にあなた様の思いを伺い、ご意思の実現に最適な方法をご一緒に考えます。

*トータルサポートが受けられる
遺贈寄付は〝遺言により″行いますが、遺言には公正証書遺言と自筆証書遺言があります。
弊事務所は文書作成の専門家である行政書士として、最適な方法をご一緒に考えご提案します。
公正証書遺言を作成される場合は、案文の起案の他、各種証明書の準備、公証人との打ち合わせや予約、証人2人の手配など手間がかかりますが、トータルでご支援いたします。
自筆証書遺言の作成も、起案、添削など安心いただけるまで支援いたします。
*遺言執行者、死後事務も任せられる
遺贈寄付が実際に行われるのはご自身がお亡くなりになった後なるため見届けることができません。
そのため信頼のおける第三者に具体的な手続きを委ねる必要があります。
弊事務所は豊富な経験に基づき、ご意思を誠実に執行いたします。
また遺言の執行と併せて、お一人様の暮らしに欠かせない生前対策から死後事務の対応までトータルでサポートいたします。
ご利用の流れ

*お問い合せ
【お客様】
お電話、メール、お問い合わせフォームからお問い合わせください。
ご質問だけでも結構です。
【弊社】
お問い合わせに対し、迅速に回答いたします。
ご依頼があれば、事務所もしくはご自宅などのご指定の場所で、詳しいご説明・ご相談に伺います。
お費用の概算をお伝えいたします。
*お打ち合わせ
【お客様】
あなた様のお気持ち、お考えを詳しくお聞かせください。
追って当方でご用意する遺言書案文の確認をご一緒にお願いいたします。
ご納得いただけましたら印鑑証明書のご用意をお願いいたします。
【弊社】
お考えを遺言書の体裁にし案文を作成いたします。
ご了解がいただけましたら公正証書作成の準備に入ります。
お費用の具体的な金額をお伝えいたします。

*遺言書の作成(公正証書の場合)
【お客様】
お約束した日時に公証役場にお出かけください。外出が困難な場合は、ご自宅や施設に出張を依頼することも可能です。
実印をご用意ください。
公証人が公正証書に仕上げた文章を読み上げますのでご確認の上、ご署名ご捺印をお願いいたします。
お費用のお支払いをお願いいたします。
【弊社】
お約束の日時に公証役場に同行いたします。
証人をお引き受けする場合は、公正証書に署名、捺印をいたします。
遺言執行者をお引き受けする場合は、公正証書の正本をお預かりいたします。

*遺言の執行
【弊社】
ご遺言の内容を誠実に執行います。ご遺産をご指定の個人や団体にお届けいたします。
お費用のご案内
| 相談料(30分) | 3,300円 |
|---|---|
| コンサルティング(1か月) | 33,000円 |
| 遺言執行者受託 | 33,000円 |
| 公正証書作成支援 | 33,000円 |
| 遺言執行手数料 | 550,000円~ |
|---|
※遺贈寄付の遺言執行の報酬は最低550,000円から、遺産(積極財産)額の1.1%です。
※印紙代、公証人手数料など、別途実費が発生いたします。
※不動産の売却を伴う場合は売却価格の3.3%を加算させていただきます。
遺産を全てお世話になった教会に遺贈寄付
子どもがいないので、自分の帰天の後は預貯金は全額お世話になった教会で使ってほしいと思っておりました。しかしいつ帰天するか分からないし、それまでは自分の暮らしもあるのでどうすればいいのか分かりませんでした。また高齢の妻が施設に入所しており、自分が先立った場合のことも悩みでした。
グレイスサポートさんに相談したところ、亡くなった後に残された財産を寄付する遺贈寄付というやり方があることを知りました。また遺贈を受けた教会に、残された妻の経済的な面倒を頼むこともできることが分かりました。
妻に毎月一定額を送金してもらうことを条件に、自分の遺産を全て教会に遺贈する内容の公正証書を作成しました。希望がかない、心配事も無くなってとても安心しました。
財産を大切なペットたちのために遺贈寄付
財産を動物愛護ため遺す
H様はご結婚されておらず、持病がおありのため万が一の手続を心配しておられました。死後の事務を委任いただきましたので、あわせて財産のことも決めておく必要がある旨をお伝えしました。ご兄弟とは疎遠とのことでしたので遺贈寄付を提案させていただいたところ、ペットをいつも大切にしてきたので、財産はペットたちのために遺したいとのお考えでした。信用できる団体に寄付したいとのことでしたので、県の動物愛護団体につき情報提供いたしました。団体の活動にご納得をいただき、遺贈先として遺言書を作成いたしました。
万が一の手続の手配と併せて、財産も有意義に遺せることになり、大変喜んでいただくことができました。
遺贈寄付をご検討なら
こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。