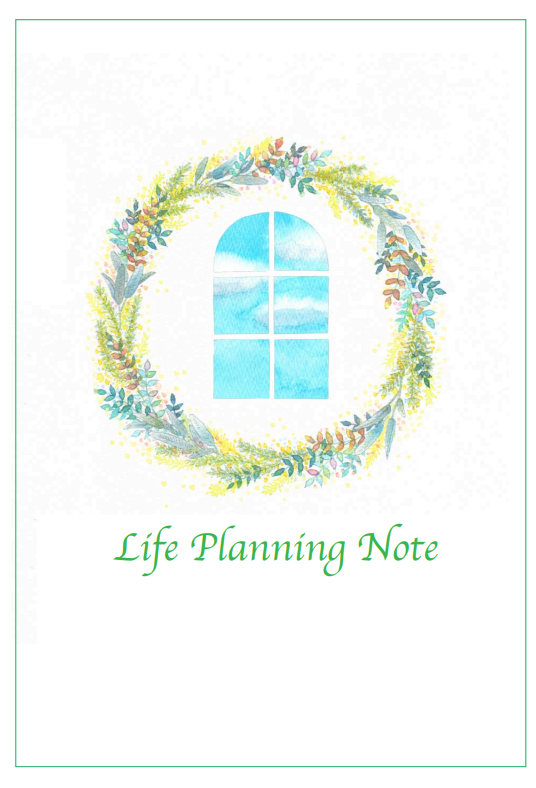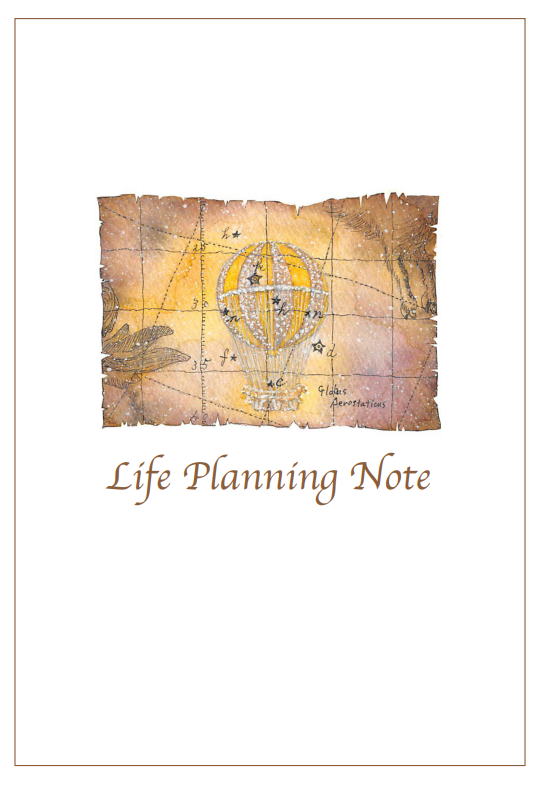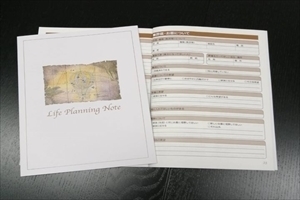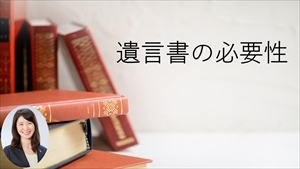簡単版!死後事務委任契約
お金がかからない方法とは?

死後事務委任契約書にエンディングノート、遺言書・・・終活で用意する書類や文書はいろいろあってややこしいですね。
「もっと簡単に、お金がかからない方法はないかな?」こんなお悩みありませんか?
こちらのページでは、簡単にできる死後事務の任せ方についてご紹介しております。
*死後事務委任契約で委任できること
*死後事務委任契約の必要性
簡単版!死後事務委任
今はそのような変化の中にあって、家族という単位にとらわれない新しい暮らしのかたちが
少しずつ形作られている過程にあるのだと思います。
お一人暮らしの方にとって特に切実なのが万が一の際の手続です。
家族に頼れないとすると、もしものときの事務手続きはあらかじめ誰かに任せておくことが欠かせません。
その一つの解決方法が死後事務委任契約です。
死後事務委任契約では下記の事務を委任できます。
具体的に何を委任するかは、受任者と相談して決めます。
*行政手続き
死亡届の提出、健康保険証や介護保険証の返納、年金手続きなど行政手続き
※死亡届への署名は任意後見契約を締結していることが必要となります
*連絡対応
事前に指定された連絡先への訃報などの連絡
*ご葬儀・埋葬対応
指定されたご葬儀、埋葬などの執行
*遺品整理
ご自宅の家財など、ご遺品の整理、形見分けなど。
*病院・施設の退去手続き
入院費用の清算、施設などの利用契約の解約、費用の清算など。
*契約の解約、費用の清算
電気ガス水道など生活インフラの契約、電話契約、クレジットカード、その他一切の生前の契約の解約手続き、費用の清算など。
*デジタル遺品の整理
サブスクやSNSなど、次々と増えるデジタル情報の整理。デジタル情報はネット上で管理されており、ご本人以外が把握することは難しいため、生前の対策が肝心です。
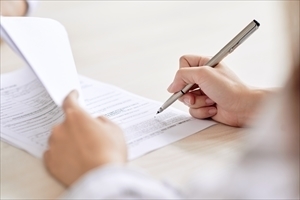
上述のように死後事務委任契約は、
万が一の際の手続、
つまり各種行政手続きや葬儀や埋葬、お墓のことや遺品の整理などを
あらかじめ専門家などの第三者に委ねておく契約で、もしものときも安心です。
頼れる親族のないお一人様には必須の契約といえます。
ただ死後事務委任契約は「契約」ですから、委任する人、受任する人双方が話あって合意をし、締結するものになります。
つまり、相手があることであり、自分の判断一つで決めることはできません。
費用も相応にかかるでしょう。
しかしご事情によってはそれでは何かとしんどい・・・
もっとお金がかからない簡単な方法はないかな・・・ということもあると思います。
そこで今回は、「契約」によらない死後の事務の任せ方をご紹介したいと思います。
遺言の付言事項を使う方法です。
まずは前提として、遺言書について簡単にご説明します。
遺言書は、死後事務委任契約書と同じく、万が一の際の決め事を記しておく文書です。
書く内容は、主に財産の相続のことです。
つまり預貯金や不動産をどうするかということを決めておきます。
それならば財産のことも、死後事務委任契約にすれば?と思われるでしょう。
しかし、死後事務委任契約書では、財産の名義変更などはできません。
民法で決められた遺言の書き方に従って文書にしないと効力を持たないのです。
お一人様にとってこの遺言書は、死後事務委任契約書と並び重要な文書といえます。
なぜならお子さんや配偶者のいない方の相続手続きは遺言がないととても大変です。
さらに相続人が全くいない方ですと財産は行く先がなく、最終的に国庫に帰属することになります。

しかし遺言を作成することで、財産を渡す相手と割合を自分で決めておくことができます。
相手は相続人以外の人でも大丈夫です。
このようなわけで遺言はとても大切なもので、遺言と死後事務委任契約が揃ってはじめて万が一の事務をカバーできます。
● 遺言で財産のことを決めておく
● 死後事務委任契約で財産以外のことを決めておく
さていよいよ、単独で作成できる遺言で、死後の事務も任せてしまう方法をご紹介します。
遺言は、法律的には「単独行為」になります。
相手のある契約とは異なり、独断で作成ができるものです。
なので相談したりするのはちょっと気がすすまないという場合でも、1人で作成が可能なのです。
この遺言に死後事務委任も兼ねさせてしまいます。
具体的な書き方をご説明します。
遺言には遺言事項と付言事項があります。
遺言事項に財産のことを書き、死後の事務は付言事項で書きます。
以下に一例をご紹介します。
遺言書
遺言者横浜太郎は次の通り遺言する。
第1条
遺言者は、遺言者が有する全ての財産を清算し、その残金を、遺言者のいとこ鎌倉次郎に遺贈する。
氏名:鎌倉次郎
生年月日:昭和30年1月2日
住所:鎌倉市長谷100
第2条
遺言者は、この遺言の執行者に上記の鎌倉次郎を指定する。
付言
次郎君、生前はいろいろお世話になりました。ありがとう。
私の葬儀は簡単でいいです。埋葬は、相模湾に散骨してください。
令和6年12月20日
横浜太郎 ㊞
上記は、相続人のいない横浜太郎さんが、財産をいとこの鎌倉次郎さんにあげる内容の遺言です。
遺言事項の第1条でその旨を定めております。
そして付言事項で死後の事務のお願いを書きます。
付言事項とは、おまけのメッセージのようなものです。
お世話になった人への挨拶や感謝の気持ちなどを書くのが一般的です。
ここに、葬儀や埋葬のことなどの要望も書いてしまうことも可能です。
遺言は契約ではないので、作成するのに相手の了解はいりません。
また自筆証書遺言であれば思い立った時にいつでも1人で作成できます。
作成するのにお金もかかりません。
いかがでしょう。
このような自筆証書遺言と、付言を使う死後事務のお願いなら気楽に用意できそうだと思いませんか?
負担なく手軽に対策したいという方はこの付言を使う方法をお試しください。
遺言書の書き方はこちらのページで詳しくご説明しております。参考になさってください。
最後に、付言を利用する方法の注意点をお伝えします。
付言を利用する方法は、相手が誰でも使える方法とは言えません。
上記の例のように、気心のしれた相手で、財産の遺贈がてら死後事務をお願いできるような場合に好適でしょう。
もしくは士業者などの専門家に委任する場合は、遺言執行の付随業務として、死後事務に対応しているか相談してみることをおすすめします(ただ専門家に任せる場合は、ある程度費用はかかるでしょう)。
また付言には法的な拘束力はありません。
そのため確実に頼みたいという場合は、死後事務委任「契約」がおすすめとなります。
● 付言を利用する方法は相手が限られる
● 付言には法的な拘束力はない
● 確実にしたい場合は専門家と死後事務委任契約を
死後に最初に必要となる死亡届の提出は、死後事務委任契約で任せることができるのでしょうか?行政手続きの専門家である行政書士が解説します。
エンディングノートを活用する終活セミナー
ー知っておきたいお一人様終活の基礎知識ー
そろそろ先のことが不安になってきたけれど、どうしたらいいのか分からない・・・。このようなお悩みはありませんか?
そんなお一人さまの不安を安心にかえるオンラインセミナーのご案内です。
エンディングノートの使い方をご紹介しながら終活全般についてご紹介。
現在の日本社会の現状と、それをふまえた必要な終活対策、遺言・死後事務委任のほか、生前対策の任意後見制度についてご説明、また空き家対策についてお伝えします。
長寿社会の現在の日本。人生の長旅に備えるヒント満載の講座です。ご自宅から、どうぞお気軽にご視聴ください!
エンディングノートからはじめる!終活講座オンライン
会 場:オンライン(YouTubeライブ)※インターネット接続環境が必要です
参加費:無料
特 典:アンケートに回答くださった方にオリジナルエンディングノートプレゼント!
終活お役立ちコラム
こちらのページを読んだ方は、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。